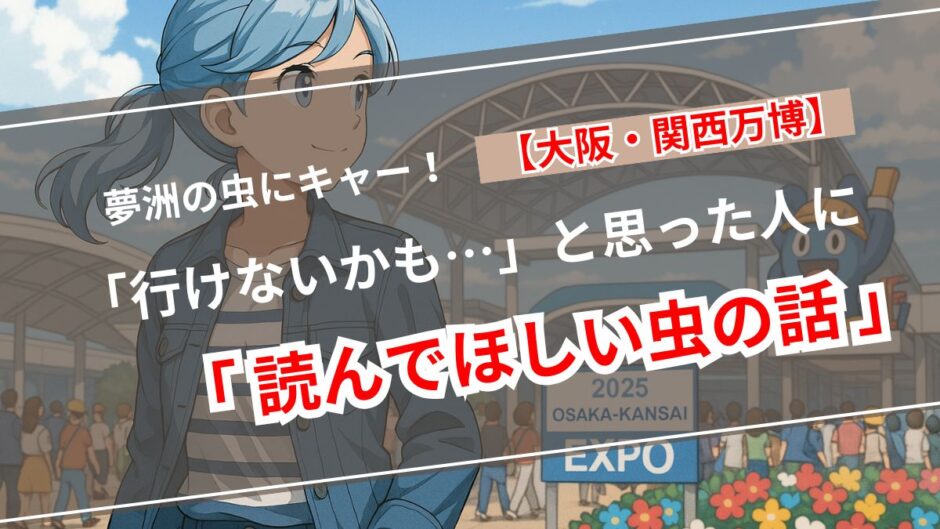「万博行きたいのに虫が無理」——そんな声に、ちょっと待ってと言いたい。
5月中旬。X(旧Twitter)では、大阪・関西万博会場に虫が大量発生したと話題に。特に「大屋根リング」の柱にビッシリと張りついた小さな虫たちの画像は衝撃的で、「もう行けない」「気持ち悪い」との声も。
でもちょっと立ち止まって、考えてみてほしいんです。
この人工島「夢洲」は、コンクリートで固められた未来の実験場でありながら、自然の生命がそこに芽吹き、息づいている場所でもあるんです。
虫が湧くのは、そこに「命の循環」がある証拠。言い換えれば、【人間だけの空間ではなく、自然との共生を模索する場】になっている——ということなのでは?
虫の正体は「ユスリカ」だった
SNSで拡散された黒い虫の正体は「ユスリカ」。
見た目は蚊のようで驚く人も多いのですが、
- 血を吸わない
- 毒もない
- 口が退化していて何も食べない
つまり「繁殖のためだけに数日だけ羽化する」非常に儚い生き物。
それが雨上がり、偶然にも一斉に羽化した。それだけのことなんです。
「虫がいる=悪」ではない。むしろ“未来”のヒントかもしれない
この万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」がテーマ。
その“いのち”とは、人間だけのものじゃないはず。
自然の命も、昆虫の命も、同じ地球上の仲間です。
虫が嫌われがちなのは分かります。でも、もしそれが「人間が快適であるべき」という価値観に偏りすぎているなら……
ちょっとその“当たり前”を問い直す、いい機会かもしれません。
万博を楽しむために|虫とうまく付き合う3つの対策
- 雨上がりの来場は避ける(ユスリカは湿気と気温上昇で出現しやすい)
- 薄手の羽織りや帽子を持参(虫除け対策に)
- 「ユスリカ=害虫ではない」と知っておく(心のバリアが下がります)
まとめ|ユスリカは“未来への問い”かもしれない
- 万博会場に虫がいるのは、夢洲が生きている証拠
- 不快かもしれないけど、それが自然のリアルな姿
- 人間中心ではない価値観への一歩になるかも
むしろ私はこう思いました。
「夢洲に、自然が戻ってきたんだな」と。
そして、万博のテーマをもう一度思い出したんです。
いのち輝く未来社会って、私たちがどんな命も受け入れるところから始まるんじゃないかなって。
「生きもの」と「未来」をつなぐ瞬間を今体験できてる。そう思えることもできるのでないかと思いこのブログを作成しました。
批判もあるかもしれませんが、一つくらいプラスの考え方をネット内にそっとおいておきます。
👉️最新の万博情報はこちら
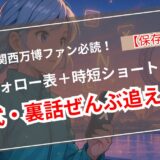 【大阪・関西万博】 “X(旧Twitter)” アカウント早見表――公式・パビリオン・ファンをひと巡りでフォローしよう!
【大阪・関西万博】 “X(旧Twitter)” アカウント早見表――公式・パビリオン・ファンをひと巡りでフォローしよう!
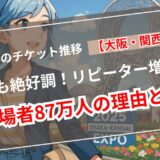 【今週のチケット推移】大阪万博、来場者378万人突破&チケット販売1,188万枚!未来に集まる人の波が止まらない
【今週のチケット推移】大阪万博、来場者378万人突破&チケット販売1,188万枚!未来に集まる人の波が止まらない  親子で未来ライフ探検隊【大阪万博】
親子で未来ライフ探検隊【大阪万博】